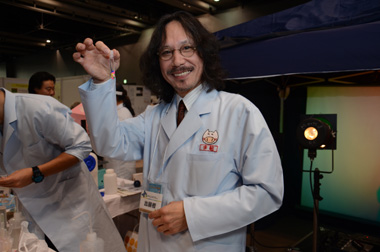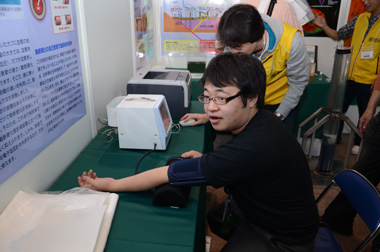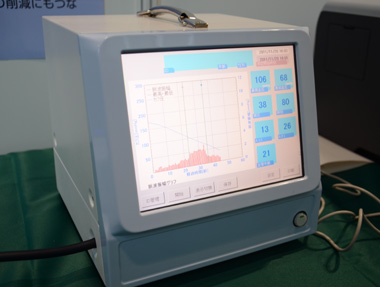函館, 科学祭
函館, 科学祭  No Comments
No Comments 演劇がつなぐ子どもとアートとサイエンス講演会
今日は中央図書館で行われた「演劇がつなぐ子どもとアートとサイエンス」
(函館高専主催)を聴講してきました!
演劇と科学が合体した講演会はいままで聞いたことがありません!

「科学する心 未来をつくる力」をテーマに美馬のゆり未来大学教授が講演。
今年の2月にイギリスのエジンバラで「科学演劇」を見て感動したことがきっかけで、函館でも演劇と科学をミックスさせた積極的な取り組みをしていきたいとしており、「これまで科学技術リテラシーの高い人と取り組んできたが、今回の講演を通じてそれ以外の方と接点を持って拡がっていけるのではないかという期待をいだいています」とお話しされました。
科学には難しいというイメージがあると思います。
最近ではそれを払しょくするために、函館では科学祭において
「サイエンスショー」「科学寺子屋」などを通じて
それの啓発をしているところでありますが・・・
教師ですら科学に関する知識とスキルに対して苦手意識があるのが課題です。
科学の知識が身につく脚本と、
演劇という子どもから大人までを魅了できる手法を活用した
「科学演劇」を通じて、子どもから大人までの理科離れを
解消することができるのではないか?ということです。
これが「科学的内容の演劇の可能性」です!
誰も手を付けていないのが重要で可能性が眠っている領域なんだと思います。
しかし、両者に共通するものを認め合ってこそ成り立つものなのかな?
科学も表現手法の一つですし、科学を活動として行うおもしろさは
「新しいことを知りたいという知的探求」などとされ、喜びにつながります。
科学する心をはぐくむことは世界を変える力、未来をつくる力になるのだそうです。

次に特別研究員の金森さんが「科学演劇の挑戦」をテーマに講演。
・函館で演劇をやっている若い人たちがたくさんいる!
・子どもの対応にたけた学科や短大がある!
・絵本読み聞かせグループもある!
ということでたたき台として科学演劇を作成。
海の科学教育に関心をもつ人たちに呼びかけて、
イカは特別な身体の構造を持っているんだよということをテーマにした
「探偵・イカずきんちゃん」を上演したそうです。
しかし課題もたくさん・・・
・誰が演じる?
・科学者が演じると演技力をつけていく動機づけ、感情移入が難しい・・・。
・ストーリー作りまではできたが演出がいない!
など。

ということで、この流れで芸術ホールの伊藤さんにバトンタッチ!
今日は心から尊敬したし、財団にはなくてはならない存在だと再認識しました!
「演劇のもつ伝える力」がテーマ。
話の流れはさすが演劇人!!!
マイクなしで、時々小芝居もいれつつ講演。
演じることは日々の中で実は多い!
ということを身体を説明していました。
今日は演劇の良くないイメージを払しょくしたい!
と何度も言っていました!
まず、日本の演劇のイメージは「暗い、難しい、やってる人だけ楽しんでる?」
という風潮があって、これには歴史的背景があるんだとか・・・
外国の文化がたくさん入ってきたときに・・・
日本オリジナルは歌舞伎など、とても海外から評価をうけた。
これのためヨーロッパの演劇文化が入ってこなかった・・・
むしろ外国人の方が遠慮したそうです。
これをうけて現代の日本においては
小さいころの学芸会の役がはずかしい。
やらなきゃいけないという義務になっている・・・
科学も演劇と同じでとっつきにくかったり、入り口がせまかったり・・・
人に何かを伝えたくてでるアクションは日々の中で多い。
たとえば、子どもに対して話しかけるときに「僕、どうしたの?」がいい例。
無意識のうちに幼稚言葉を話す。
モノマネをしたほうが早かったりする。
これが演劇。
「ありがとう」という言葉ひとつにとってみても、言い方ひとつですべて印象が変わってくる。日常の中で使い分けている。
チケットを買って観劇するだけが演劇じゃない。
より伝えたいから、無意識のうちに演技をしている。
これも演劇。
どうやったら喜んでもらえるだろうという意識。
観客を意識しない舞台はぜんぜんおもしろくない。
昼ドラもニーズがあるから続く。ターゲットと仕掛ける側がマッチしている。
演劇の持つ可能性は、ゴールが遠い科学実験と同じで、嘘くさい話を毎日稽古していくことでほんとっぽくなっていく。すべては伝えたいということだけのために。←うんうん!!!
伝える力と伝わる力が強いのが演劇のウリ。人に与える印象が強い。
いままでみなさんが抱えている演劇の暗いイメージではなく、少しでもおもしろいものであると思ってもらって、日常から自然発生する楽しい演劇のイメージで科学演劇につなげてもらえればとのこと。
これまで科学と演劇は全然であったことのない同士。
科学と演劇がどうつながっていけるのか尽力したい!とのこと。

最後はパネルディスカッション
科学も演劇も「悪いイメージを抱えている問題は同じだった…」
ということ。
函館において科学演劇は実現しそうですか?との美馬先生の問いに・・・
「アンサンブルではなく、こちらが引いてそっちを美しくというコラボレーションの精神で、共通の落としどころを探してから取り組めばいいと思います。」
と伊藤さんはコメント。(激しく同意)
函館では自分たちが楽しむことが先行している劇団が多いため、
科学を伝えるだけでなく、作ってる自分たちも楽しむことを忘れてはいけないと金森さん。
下記に質疑応答で印象に残ったことだけ記載します。
○シナリオの力と演者の力にどちらに比重をおくか?
→役者の技量も問われるが脚本に比重を置く。(伊藤さん)
○演劇を志す人にコーディネーターとしてどのような覚悟で接しているか?
→DVDだけでは感動は残らない。温度やにおい、お客さんの熱気も舞台の魅力。生モノのもつよさ。自分がそうだったように・・・人の人生を変えるかもしれないという覚悟で臨んでいる。演劇には人に与える力の強さがある。(伊藤さん)
○お祭りという視点
→時代の流れは速いので、仕掛ける側の柔軟性が大事。自分たちのオリジナリティをどう伝えていくかが課題。(伊藤さん)
○どのあたりまで科学と演劇とで共有するか?興味をもっている演者はいるのか?どうやって興味をもたせられるのか?
→かけ離れているもの同士でものを作っていく面白さを大切に、絶対にぶれないゴールだけを作っておく。(伊藤さん)
アイディアをもって、ビジョンを共有し、社会にどのようなインパクトをあたえ、自分の分野へもインパクトを与えられるかを考えながら取り組むことで興味にもつながる。それがこの企画への期待とおもしろさ。(のゆり先生)
最後に美馬先生が、ジャンジャックルソーの言葉を引用・・・
「劇場もいらない。くいをたてて花でかざる。人があつまって祭りが起きる。市民全員が演者になる。」
とのことです。
私見ですが・・・
科学と演劇が互いの魅力を認め合いつつ、
それを活用しながら両方が持っている悪いイメージを払しょくしていけば、
互いに原点回帰するきっかけにもなるし、
WinWin関係にも十分なりうると思います!
非常に内容の濃い講演会でした。
それにしても今日の伊藤さんは熱かった!!!
———————–
5位を維持!何が起きてる!?w
クリックお願いします!
↓
![]()